スタッフブログnakata Labs なかたラボ
春のガーデントーク
更新日:2013年4月29日(月)
本日、nakata Labsのレクチャー「春のガーデントーク」を開催しました!
これまで、初夏、秋、冬と開催してきたこのイベント、
美術館の庭園と裏山を、植物の専門家・浜田展也先生と一緒に散策しよう!という企画です。

お天気に恵まれた今日は、ガーデントークにうってつけ。
花も、まだまだ色んな所に咲いていました。

例えばこのイロハモミジ。
葉の下の、小さな小さな赤い丸が「花」だそうです!
この小ささの中に、きちんと雄しべも見えました。
モミジに花が咲いてるなんて、いままで考えたことがなくて新鮮!
カエデは広島県の木でもありますね。
足下には、小さなスミレ、トキワハゼ、蛇のようなジャゴケやスギゴケ、シダの仲間のイヌワラビなどなど・・・。

ほんの小さなスペースの中に、たくさんの植物たちが集まっています。

これから庭園の主役になっていくのはツツジ。
たくさんの種類があり、大きく分けると、もともと東西で分布が異なっていて、
その境界線は岡山市の真ん中あたりにあるのだそうです。

東日本由来のモチツツジは、花の付け根がペタペタとしていて指にくっつきます。
西日本のものは、もともと岸に咲いていたキシツツジ。
雄しべの数も、10本と5本とで違います。
それぞれ植物には「基本の数」があって、例えば花びらが5枚なら、雄しべも5の倍数というふうに、法則があるそうです。
身近なツツジですが、意外に知らないことだらけでした。
実は「毒」がある!というのも初めて知りました。(みなさんご存じでしたか?)
葉っぱをたくさん食べたりしないほうがいいみたいです。
花がすぼまっているこちらは、ドウダンツツジ。

ちょっと似ていますが、スズランのような可愛らしい花をつけたアセビ。

漢字で書くと「馬酔木」で、これにも毒があり、馬がフラフラになってしまうからとのこと。
でも、ほんとうの馬や牛はよく知っていて、放牧していたような場所でも、
アセビやツツジの仲間などは食べずに残されているそうです。
春におなじみのモクレン。

あらゆる植物のグループと同じDNAをもっていて、原種に近いのだそうです。
原種に近い=雄しべや雌しべがたくさんあるのも特徴のひとつとのこと。
こちらはオオデマリ。

ぱっと見はアジサイに似ていますが、実は花のつくりが異なっていて、
アジサイは、四つのガクが分かれて花びらのようになっていますが、
こちらは、花びらの根元がくっついたラッパ状になっています。
ツツジなんかもラッパ状ですね。
ツバキもまだまだ見頃です。

こちらはボトルブラシツリー。
試験管を洗うブラシにそっくりです。

ローズマリーの花。

可愛らしい花の間からのぞく枝。
中が空洞なこちらは「空木」=ウツギの仲間のヒメウツギ。

彼は、本日いちばん熱心にメモ&スケッチをしてくれていました。
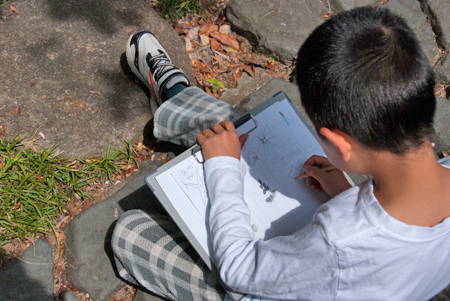
どんどん裏山に登っていきます。

一体どこにいるのだか、忘れてしまいそうです。

こちらは、松に似てますがヒマラヤスギ。
真新しい葉がみずみずしいです。

陽射しはあたたかくて、木陰はしっとり気持ちよくて、緑が輝いていて、しみじみ良いなあと思いました。
(あと、蚊もまだ出ませんし・・・。)

そのほかにも、たくさんの話を伺いました。
花びらも雄しべも雌しべも、もともとはそれぞれ葉っぱだったこと。
つまり、種のもととなる胚珠や、雄しべの先の花粉が入っている部分(ヤク)も、
葉っぱを折りたたんだところから始まったのだそうです。

また花びらは、花が「こいつに花粉をつけてもらいたい」と思っている(?)
虫や生き物に合わせた形に進化しているのだということ。
小さくすぼんでいるのは、小さな虫だけを入れるため。
東南アジアでは、細長くて、奥行きが30cmもあるランの花に合わせたかのように、
30cmもの口吻をもつ蛾がいること!などなど。
想像するとちょっと恐いですが、虫と花が一緒に進化してきたなんて、偶然にしては、できすぎ!
ほんとに奥が深くて不思議で、わくわくします。

あっという間の90分。楽しいガーデントークでした。
浜田先生、ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました!
庭園と裏山は、美術館かレストランをご利用いただければ、散策していただくことができます。
今まさに散策にピッタリの季節です。
未体験の方はぜひぜひ、歩きやすい靴で美術館に来て、植物の世界も楽しんでみてくださいね。
